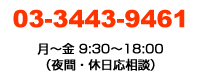将来債権の譲渡は長期間でも有効――最高裁の新判決
Q これまでは将来の一年分しか譲渡が認められていないと考えられていた、将来発生する診療報酬債権の譲渡について、平成一一年一月二九日に最高裁第三小法廷で新しい判決が出たそうですが。
A これは譲渡人(医師)が借金を返すため、第三債務者(社会保険診療報酬支払基金)から支払われる将来の診療報酬債権を譲受人(リース会社)へ八年三か月分を予め担保として譲渡する契約について、最高裁が有効と認めたものです。
Q これまでの判例は、どうなっていましたか。
A 最高裁第二小法廷の昭和五三年一二月一五日の判決が、契約締結後一年の間に医師に支払われる診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約を有効としたため、これまではこの判例を根拠にして将来の債権譲渡は一年間に限るように理解されていました。しかし今回の新判決はこれを否定して、昭和五三年の判決は一般的な基準を明らかにしたものではないと明言しました。
Q 新しい判決の意義はどういう所にあるのでしょうか。
A 新しい判決自らがいうように、「将来有望でありながら、現在は十分な資産を有しない者に対する金融的支援が可能になる」点に意義があります。身近な例でいえば、若い医師が診療所を開設するため借金したいとき等です。
Q この判決はこれからどのように活用されると思われますか。
A 経済界では債権の流動化に役立つものと考えられています。特に平成一〇年一〇月に施行された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により認められた債権譲渡登記を利用することにより、その効果は大きくなります。
Q 将来の債権はどのように譲渡すればよいのでしょうか。
A 譲渡の始期と終期を明確にし、譲渡の目的債権を特定しなければなりません。
Q 将来見込みに反して債権が発生しないときはどうなりますか。
A 債権が見込みどおり発生しなければ、債務不履行として譲受人が譲渡人の法的責任を追及し、回収ができない額は譲受人の損となります。
Q 譲渡するについては、何の制約もないのですか。
A そんなことはありません。不当な内容だと無効になります。契約締結当時の譲渡人の資産状況等から、「期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与えるものであると見られるなどの特段の事情の認められる場合には、右契約は公序良俗に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定されること」があります。
Q 具体的にいうと、どういうことですか。
A 例えば、将来の収入を長期にわたって全部譲渡させて、譲渡人の生活が成り立たなくさせるようなことは許されないのです。
代理受領の委任状
Q 当社A(債権者)は取引先B(債務者)に対し債権がありますが、債務者Bの当社Aに対する将来の支払が不安なので、債務者Bの売掛先C(これを第三債務者といいます)に対する債権を担保にとりたいのですが、どうしたらよいですか。
A B社から、B社のC社に対する債権をA社に譲渡したという文面の内容証明郵便をC社宛に出して貰う方法、つまり債権譲渡による方法が最も有効です。
Q わかりました。しかし、B社とC社との間に「B社はC社に対する債権を、C社の承諾なく第三者に譲渡してはならない」との特約がある場合はどうですか。
A その場合は、A社はB社から代金取立の代理権を授与してもらい、B社の代理人としてC社におもむき、C社から代金を受け取ってこれをB社に対する債権の弁済に充当する「代理受領」の方法が採られます。
Q 代理受領には問題点はないのですか。
A 債権譲渡の場合、C社はA社に対してしか支払が出来ず、間違ってB社に払っても、A社もC社に支払を求められます。又、内容証明で通知することにより、それに後れた債権の二重譲渡にも対抗できますし、その後B社の債権者から差押えられる心配はありません。
しかし、代理受領の場合だと、C社がB社に支払っても、一般には文句が言えず、B社の債権者が差押えてきた場合、A社はその債権に質権を設定しておかない限り対抗できません。さらに民法第六五一条により、B社は何時でも代理権を解除できます。
Q それではどうすればよいのでしょう。
A A社とB社で代理受領の委任契約を結ぶとき、①委任者Bは受任者Aの同意なしに委任を解除しないこと、②弁済の受領は受任者Aだけが行い、委任者Bは受領しないこと等、の特約を結ぶことが必要です。
Q それでC社に対抗できますか。
A それだけでは対抗できません。三者契約で代金は必ずA社に支払い、B社には支払わない、とC社にも調印させるのが最も確実ですが、実際問題として中々困難です。そこでA社とB社の特約(委任を解除しない。受領は受任者のみが行う)の入った委任状をC社の処へ予め持参し、「右承諾します」と記名、捺印して貰うのです。そうしておけば、もしC社がB社に支払っても担保権を侵害したことになり、A社はC社に損害賠償の請求ができます。
Q なるほど、そこまでしておけば、後でB社が他者D社に債権譲渡し内容証明で通知した場合でも対抗できるのでしょうか。
A 元々代理受領は工事請負代金のように債権譲渡禁止特約のあることが取引業界において普遍的慣例の場合に用いられ、その場合は後に債権譲渡を受けたD社は悪意者として保護されません(民法第四六六条二項)。
しかし、そうした慣行のない業界で後に譲受けたD社が善意の場合、やはりD社への債権譲渡の方が優先し、A社はB社に損害賠償請求できるに過ぎませんが、B社に資力がなければ効を奏しないことになります。
従って代理受領の方法を採る場合は、こうした法律的弱点を充分に把握し、前記の特約に個人保証をつける等、細心の注意を払う必要があります。
危急時遺言について
一 病気や交通事故などで重体となった人が遺言を残したいと希望した場合、どうしたらよいでしょうか。
その人が自分で文章を書くことができる状態であれば自筆証書遺言を作成すればよいのですが、文章を書くことができない状態のときには、「危急時遺言」という方式の遺言をすることができます。
危急時遺言というのは、病気や怪我などで死に直面している人が、自分で文書を書かなくても、又、署名することすら必要でなく、第三者に口述するだけで作成することができる遺言の方式です。
二 この危急時遺言が有効となるための要件は次のとおりです。
①病気その他の理由により死亡の危急に迫っていること
②証人三人以上の立会があること
③遺言者が証人のうち一人に遺言の趣旨を口述し、その証人がこれを筆記すること
④筆記した証人がその全文を遺言者及び他の証人に読み聞かせること
⑤各証人が筆記の内容が正確であることを承認し、署名捺印すること
⑥遺言の日から二〇日以内に、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に請求して遺言の確認を受けること
⑦但し、遺言者が普通の方式の遺言をすることができるようになった時から六ヶ月間生存したときは危急時遺言は失効する
三 危急時遺言では、他の方式の遺言と異なり、特別に、家庭裁判所による遺言の確認の手続が必要です。
遺言の確認というのは、遺言が遺言者の真意に出たものかどうかについて、裁判所が確認する手続です。
この確認の審判の際には、遺言者が生存していれば、裁判所が直接遺言者に面接するなどして真意を確認しますし、遺言者が死亡していたり、意識不明の状態の場合には、遺言が遺言者の真意に基づいたものか否かについて、医師、看護婦その他の関係者などから事情を聞くなどして、詳しい調査がなされます。
したがって、危急時遺言をするときには医師の立会を求めるなどして(証人になってもらってもよい)、後日の遺言の確認のための準備をしておくことが肝要です。遺言者や証人が作成した遺言にかかわるメモなども確認のためには有用な資料となりますので捨てずにとっておくべきです。
四 危急時遺言を執行するためには、遺言の確認に加えて遺言の検認も必要です。
遺言の検認というのは、遺言の形式その他の状態を家庭裁判所が調査確認するための手続で公正証書遺言以外はすべての遺言で必要とされているものです。
なお、遺言者が重体であっても、時間的に公証人に来てもらうだけの余裕がある場合には、危急時遺言を作成するのではなく、公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成したほうがよいでしょう。公正証書遺言であれば、確認や検認の手続は不要です。